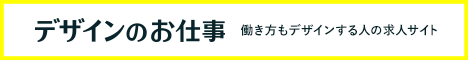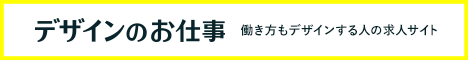公開審査としては4回目となる「JCDデザイン賞2005」の審査会が、去る6月21日、東京デザインセンター(五反田)にて行われました。
審査員を務めたのは、委員長の飯島直樹氏をはじめ、青木 淳氏、近藤康夫氏、杉本貴志氏、橋爪紳也氏、それに特別審査員であるクライン・ダイサム アーキテクツという顔ぶれ。
ここでは応募総数343点の中から大賞決定に至るまでの経緯と受賞作品についてご紹介します。

審査員の方々: (写真左から)
マーク・ダイサム氏/アストリッド・クライン氏/青木 淳氏/杉本貴志氏/近藤康夫氏/橋爪紳也氏/飯島直樹氏
|

◆ 予備審査 ◆

− 一次審査と二次審査 −
公開審査に先立ち、午前中に一次審査と二次審査が非公開で行われました。審査は比較的スムーズに進んだようです。審査方法は例年通り。長机に並べられた作品パネルに審査員が付箋紙を貼って投票します。結果、多数の票を得た作品を選定していきます。
一次審査で応募総数343点の中から85点を選出。さらに二次審査で入賞(奨励賞)39点
を選出しました。それ以外の46点については、この時点で入選が確定しました。

◆ 公開審査 ◆

− 今年の作品はレベルが高い −

飯島直樹氏
|
午後からは、いよいよ公開審査会。

橋本夕紀夫氏による開会挨拶の後、審査の進行を務める飯島氏が今年度の応募作品について述べました。
「今年の作品は全体的にレベルが高く、文化・公共施設部門やその他の部門では新しい響きを感じさせる作品が多く寄せられました。飲食店舗部門については、似通った作品が集中した昨年と比べ、少し趣に変化が見られましたね」
また、増加の傾向が見られる海外作品についても飯島氏は触れます。
「今回は台湾、韓国、香港から計27点の応募がありました。毎回JCDではアジア以外の国々へも広く公募しています。今後、ますます海外作品の応募が増えることが期待されます」
世界の視点で日本デザインを検証することを目指す同賞。海外からの注目度も年々高まりを見せつつあります。当日は韓国の建築やインテリア雑誌の出版社が取材のため来日。また、スウェーデンからは、デザインを学んできたと言うお二人が審査会を聴講しに訪れていました。


− 厳正なる審査 −
いよいよ審査開始…と、その前に急遽、飲食店舗部門の奨励賞について再検証する時間が設けられました。二次審査で票が分散し、予定よりも多くの奨励賞がノミネートされたためです。
付箋投票と議論が交わされ、最終的に4点を奨励賞に決定しました。途中「記号で組み合わされたデザインはそんなにおもしろくない」「目新しい要素がない」といった厳しい意見も飛び交い、すでに白熱する審査会。賞決定にあたり審査員の真剣さ、そして慎重さが伺えました。


− 三次審査開始 −
10分程度の後、ようやく今回のメイン審査に移ります。
ここでは奨励賞39点の中から各部門で優秀賞を決定。さらに大賞1点と特別審査員賞1点、35歳以下を対象とした新人賞数点を決定します。

三次となる同審査も、まずは付箋投票による選定方法が採られました。部門ごとに順に投票、選定が繰り返され、目安とされた1〜4点の優秀賞を各部門で決定。選出された計15点は大賞候補となり、次の審査へ駒を進めます。



「karaoke-tub」
|
注目はイキイキとした作品が寄せられた“その他の部門”。同部門では奨励賞3点から優秀賞1点を選出します。作品のひとつ「karaoke-tub」は、住宅のカラオケルームをバスルーム風に設計したもの。同作品に票を入れたクライン氏は
「私達にとって、心近い作品です。2カ月前にロンドンのAAスクールで行ったインスタレーション作品“バーチャルバス”にとても似ている!白い床にタブ、シャワーを設置したデザインも。コンセプトはシャワー音を聞きながら、お風呂の中にいるような空間を体感するというものでした」とコメント。
しかし、結局クライン氏の思いは届かず、優秀賞には「c-MA3」が決定しました。


|

|

審査会場の様子。奥には審査会のアシスタントも務めた学生達が聴講。
|

非公開で行われた予備審査の様子。
|

飲食店舗部門の奨励賞を再検証する審査員。
|

三次審査開始。
|

写真右から近藤氏、ダイサム氏。
|

ライブカメラで審査の手元が映し出される。
|

審査の合間には飯島氏(写真右)が各作品のコンセプトを簡単に説明。デザイナーの小泉誠氏(写真左)が審査会のアシスタントを務めていた!
|

プレゼンパネルを見入る審査員達。
|

プレゼンパネルを見入る橋爪氏。氏の背景を読み取ったコメントは明快だった。
|
|