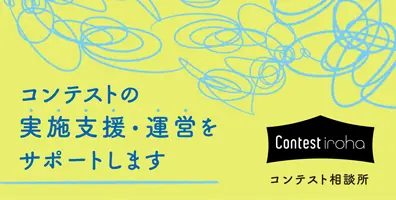職人とデザイナーで磨き上げた新たな伝統工芸のカタチ。「東京手仕事」商品開発プロジェクト受賞者インタビュー1 / 2 [PR]

江戸切子や東京染小紋、江戸木目込人形など42品目が指定されている東京の伝統工芸品。江戸時代から脈々と受け継がれてきた職人の技を、未来につなげていくためのプロジェクトがあります。
「東京手仕事」商品開発プロジェクトは、繊細な技術を持つ職人とデザイナー等のビジネスパートナーが協働することで、新しい「東京の伝統工芸品」を生み出す取り組み。2015年から公益財団法人東京都中小企業振興公社が主催し、職人とデザイナーのマッチングから商品開発中のアドバイス、試作品制作の費用支援などをおこない、実際に商品として完成するまでをサポートしています。令和6年度は6月3日から6月28日まで、企画デザイン案等を含むPRシートを募集します。

今回お話をうかがうのは、令和4年度の同プロジェクトにて東京都知事賞を受賞した、和酒専用江戸切子「蛇ノ目切子」のデザイナー・松尾慎さん。普段はフリーランスのデザイナーとして商業施設や住宅などのインテリアデザイン、収納家具の開発など、空間を軸にデザインを手がけています。そんな松尾さんがなぜ本プロジェクトに参加し、どのような想いで「蛇ノ目切子」をデザインしたのか、うかがいました。
コンペを通して、幼い頃から身近だった工芸に挑戦
――まず、東京手仕事商品開発プロジェクトに参加された経緯からうかがいたいと思います。伝統工芸品にはもともと興味があったのでしょうか?

松尾慎 デザイナー。京都市立芸術大学環境デザイン専攻を卒業後、設計事務所に就職。その後、1995年に松尾慎デザイン室を設立、インテリアデザインをベースに、家具や伝統工芸品などのデザインに携わる
出身が佐賀県の有田に隣接する武雄市で、父が陶芸家だったので幼い頃から父の工房に入り浸り、粘土遊びをするのが日常でした。なので工芸との距離はずっと近かったと思います。学生時代には環境デザインを専攻し、卒業後は建築事務所に就職。その後フリーランスとしてハウスメーカー等の仕事をしながら、私自身も焼き物づくりに挑戦するようになりました。
クラフト系の公募展にも作品を出展するようになり、そんな中で出会ったのが東京手仕事商品開発プロジェクト。あらゆるデザインコンペ情報がまとめられている「登竜門」で見つけたのがきっかけです。腕試しだけでなく、入賞したら案件化するような、仕事につながるコンペに参加したい。加えていままで身近だった焼き物以外の工芸にもチャレンジしたい。そんな想いから本プロジェクトは自分にぴったりだと思い、応募しました。
――松尾さんはこれまでも、東京手仕事商品開発プロジェクトに参加されていたそうですね。
プロジェクトの存在を知ってからここ5年はほぼ毎年応募しています。木彫から、漆器、べっ甲……いろいろな工芸品にアプローチしてきました。近々では、令和2年度に江戸木目込人形の職人さんとマッチングし、ありがたいことに優秀賞をいただきました。それ以降もプロジェクトへの参加を継続して、令和4年度は江戸切子を手がけるGLASS-LABさんとマッチング。「蛇ノ目切子」をデザイン、商品化することができました。

左がGLASS-LAB株式会社と協働で商品化した「蛇ノ目切子」。右はプロジェクト後、GLASS-LAB株式会社が独自に製作した一回り小さいぐい呑みサイズのもの
日本酒器の定番を江戸の伝統技術で表現する
――東京都知事賞を受賞した「蛇ノ目切子」について、デザインに込めた想いを教えてください。
ビールにはジョッキ、ワインならワイングラスというように「日本酒を注ぐならこれ」という新たな定番の器をつくりたい。そんな想いから「蛇ノ目切子」ははじまりました。
日本酒は年々海外への輸出量が増えて、特に純米大吟醸などの高級な日本酒が人気を博すようになりましたが、一方で国内では年々売上が減少し、業界全体の売上は右肩下がり。日本酒を楽しむ人が年々減っている、そんな現状に私自身もったいなさも感じていました。
日本酒の楽しみ方は、味だけじゃない。注ぐ器によって見た目や香りの広がり方がまったく違うんです。日本酒器の新定番をつくることで、多くの人が日本酒を楽しむきっかけになればと、今回のデザインを発想しました。
――蛇ノ目模様を採用した理由はなんだったのでしょうか?
日本酒のつくり手である杜氏さんが、できあがった日本酒の品質を確認する利き酒をおこなう時、一合サイズの蛇ノ目酒器が使われます。お酒のわずかな黄みと透明度を見極めるのに、青色で描かれた蛇ノ目が最適なのだと。さらに味とともに、香りを確かめやすくするために口が大きい必要があるんです。

視覚と嗅覚と味覚、すべてを研ぎ澄まして飲める設計。このデザインこそ定番化すべきだと思いました。加えて本来は陶器が使われていますが、ガラス細工なら底の蛇ノ目も外側から見える。伝統的な定番を取り入れつつ、新しい見せ方ができるのではないかと考えました。
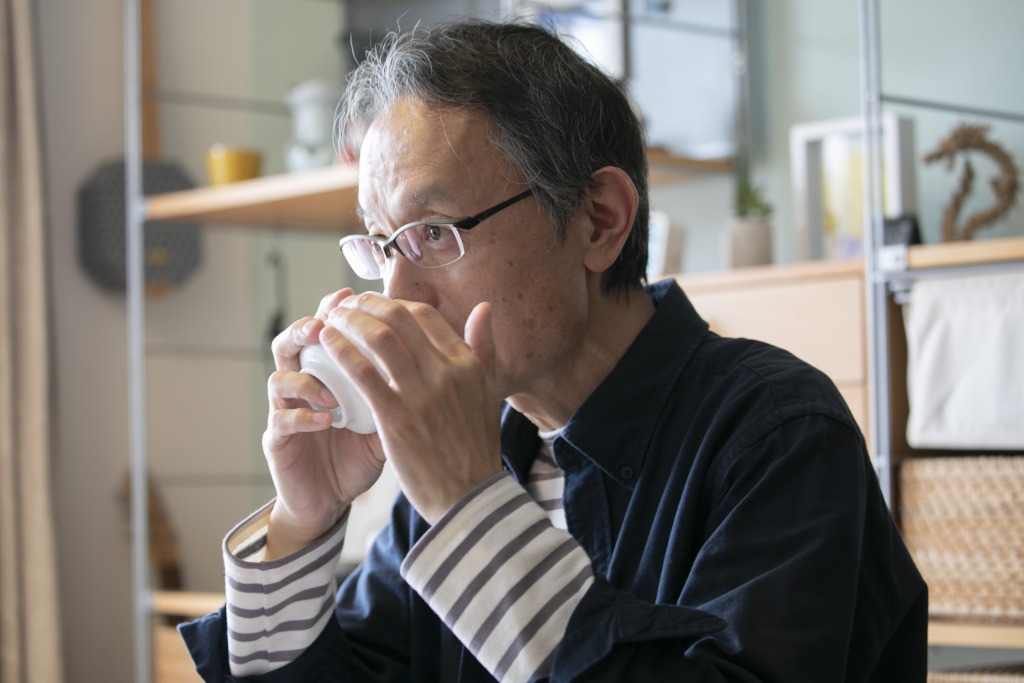
――マッチング会の時、GLASS-LABさんは松尾さんのデザインに一目惚れして即決されたとうかがいました。ご自身ではどの部分が刺さったのだと思いますか?
その話ははじめて聞きました(笑)。そう言っていただけてとてもうれしいです。自分としてはコンセプトに賛同いただけたのが大きかったのではないかと思います。日本の伝統文化である酒造りで使われる器を、GLASS-LABさんが得意とする平切子とサンドブラストの技術で美しく表現する。そこに新しい可能性を見出していただいたんじゃないかと。
![コンテスト情報サイト[登竜門]](https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/compe/img/common/logo_trm.svg)