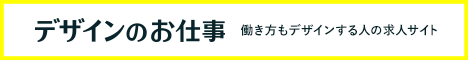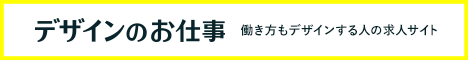|
|
 |
 |
|
受賞作品発表 2010年10月
|
 |

 |
 |
|
|
 賞・賞金 賞・賞金 |
 |
●大賞 (1作品) 賞牌、賞金100万円
●佳作 (2作品) 賞牌、賞金30万円
●三菱化学賞 (1作品) 賞牌、賞金30万円
●審査員特別賞 (10作品) 賞牌
|
|

|
|
|
 審査/審査員(敬称略) 審査/審査員(敬称略) |
 |
■審査員長
水野 誠一(ソシアル・プロデューサー)
■審査員
石井 幹子(照明デザイナー)
榮久庵 憲司(インダストリアルデザイナー)
向井 周太郎(武蔵野美術大学名誉教授、デザイン研究者)
柏木 博(武蔵野美術大学教授、美術評論家)
河原 敏文(プロデューサー、ディレクター、CGアーティスト)
坂井 直樹(ウォーターデザインスコープ代表、コンセプター)
都築 響一(編集者)
日比野 克彦(アーティスト)
茂木 健一郎(脳科学者、ソニーコンピュータサイエンス研究所 シニアリサーチャー)
■特別審査員
冨澤 龍一(株式会社三菱ケミカルホールディングス 取締役会長、三菱化学株式会社 取締役)
|
|

|
|  |

*各作品をクリックすると、全画像がご覧いただけます
(作品名、受賞者名、出身校、制作意図)
|

|
 |
オリツナグモノ
堀 崇将
金沢美術工芸大学大学院 美術工芸研究科 デザイン専攻視覚デザインコース
水鳥やウミガメなど多種多様な生物が共存する巨大な一つの生態系、海。しかし今日、その海は人間の出すゴミによって汚され、そこに棲む海洋生物たちが生存を脅かされる事態が起きています。『オリツナグモノ』はこの海洋生物の多様性をテーマに、それに対する人々の問題意識を喚起させることを目的にした作品です。
|
 |

|
 |
変化する数え方
小倉 誉菜
多摩美術大学 造形表現学部 デザイン学科
数え方は、同じ「もの」でも捉え方や見方によって数え方が変わったり、状況や状態によっても変化します。また昔使っていたもので今ではあまり使われなくなったものは、数え方もあまり使われなくなっていたり、逆に新しい数え方ができたり、進化したりと、日本の文化と密接に関わっています。一方的な視点から見るのではなくて、変化していく一連の流れを見せることによって、より分かりやすく楽しく覚えることができると思います。
|
 |

|
 |
VISION
物袋 卓也
[共同制作者]山本 哲也
神戸芸術工科大学 デザイン学部 プロダクトデザイン学科
コンセプト「思い出の一瞬を切り撮る。」
指で撮りたい範囲を囲むとその形に切り取られ写真として残すことができるカメラのアドバンスデザイン提案。従来のカメラは結果を楽しむことがメインになっていましたが、本提案では撮影する状況、撮り方といったところに焦点をあて撮影をする過程も楽しむことができるカメラとユーザーとのこれからの関係を提案しました。
|
 |

|
 |
局地用間伐材運搬装軌車両 モクザイル-2400
小島 拓也
武蔵野美術大学 造形学部 工芸工業デザイン学科
日本の山から間伐材を運び出すためのトランスポーターの提案。東京都日の出市の山でのリサーチを基にデザインした。日本の森林の40%を占める人工林では「間伐」と呼ばれる木の間引きが必要とされている。しかし間伐された木材の90%は山に道がないために運び出すことができないまま山に捨てている。道のない山を走行し、荷台を回転させ、クローラーをベルトコンベアのように使うことにより傾斜地でも荷台に木材を積み込む。この提案により日本の林業の繁栄と、森林の保全を願う。
|
 |

|
 |
時の標本 - Specimen of time -
玉田 裕美
武蔵野美術大学 通信教育課程 造形学部 デザイン情報学科
砂時計の世界では、ガラスの器が世界で、砂は「時」そのものである。砂の落下はガラスの中に<過去→現在→未来>という「時」の流れを生み出す。今回私は、そんな哲学と物理学の両方を兼ね備えた砂時計を用い、「時」を「標本」として具現化させた。言葉で表される「時」、珍しい「時」、五感で感じる「時」など。私が採取した30の「時の標本」を通し、「時」を表す言葉が持つ、美しさや面白さに触れていただければ幸いである。
|
 |

|
 |
CHESS
藤井 準子
[共同制作者]粕谷 顕二
エスモード・ジャポン大阪校 総合科 モデリズム専攻
細やかな構造で、大きく美しいボリュームを魅せる“構造美”。これをコンセプトに、“チェス”の6種類の駒各々の特徴を1体1体に凝縮させたコレクション。一見バラバラに見える様だが、生物的なライン、圧倒的な存在感などの点で一貫させ、異様でありながら美しい洋服を表現した。コレクションとは魅せるもの。観る人を感動させる。そんな思いを込めた、私たちの洋服づくりに対する情熱を感じてほしい。
|
 |

|
 |
tension
江畑 潤
静岡文化芸術大学 デザイン学部 生産造形学科
脚の細さを究めたスツール。建築に用いられるスケルション構造(ブレース構造と張弦梁構造を組み合わせたもの)に着想を得た。脚に張られたワイヤーにより部材の座屈や曲げに抵抗し、最小限の部材と細さで、スツールとして十分な効果を発揮している。直径6mmのステンレス材の脚に因る緊張感や浮遊感は、座る行為に新しい楽しみを生み出す。細さや軽さ、少なさ。最小限への憧れや挑戦は、環境保護への姿勢と結びつくと考えた。
|
 |

|
 |
葉っぱのような、紙のような
大橋 彩佳
武蔵野美術大学 造形学部 基礎デザイン学科
この研究は、葉が、その厚みや重さが紙とよく似た要素や性質を持つことに気付き、葉の変様を紙で表現することから始まりました。研究を進めるにつれて、それとは逆に、紙に起こる現象の中にも葉のそれとよく似たことが起きていると気付きました。ここから「葉っぱのような紙」と「紙のような葉っぱ」というそれぞれ12の現象からなる作品群をつくりました。
|
 |

|
 |
pantoxin
小尾 真理子
武蔵野美術大学 造形学部 視覚伝達デザイン学科
有毒生物は体色によって毒があることを表現している。これは警戒色と呼ばれているが、果たしてどのような色彩から我々は毒を感じ取るのだろうか。「毒々しい」という言葉があるが、具体的にどのようなものが毒を感じさせるのか、定義がないことに気がついた。体色と毒の強弱、生態ピラミッドとの関係性について研究し、その関係性が一目でわかるよう、100体の有毒生物の体色を抽出した立体のダイヤグラムを完成させた。
|
 |

|
 |
Clam-Bone
小野村 隆男
武蔵野美術大学 造形学部 工芸工業デザイン学科
初めてでもすぐに演奏できる電子楽器。
楽器に触れたときに最初に演奏の体験をすることによって、苦手意識を作ること無く楽器を始めることができる。
|
 |

|
 |
See You Again
坂本 雄祐
東京藝術大学大学院 映像研究科 メディア映像専攻
この作品は、「少し前の自分」と「さらに少し前の自分」、そして「現在の自分」を同時に映像上に共存させるインスタレーションである。3つの空間にはスクリーンが用意されており、そこに「過去の自分」と「現在の自分」が重ねて映し出される。鑑賞者は複数の自分が映っている映像を見ていると、自分の「自分らしさ」によって自己像の認知が撹乱され、どれが「現在の自分」なのかわからなくなるという特殊な体験をすることになる。
|
 |

|
 |
75%HOUSE
外山 真理子
武蔵野美術大学 造形学部 基礎デザイン学科
「比率の体感」:例えば今回は「CO2 25%削減」という環境問題にまつわるスローガンをヒントにしました。「25%」という数字は具体的ですが「環境問題」という世界規模であるということと「CO2」という目に見えない物質のおかげで「25%削減」がどれくらいなのか具体的ではありません。「25%削減」とはどれくらいなのかを環境問題として真っ正面から切り込むのではなく、まず「比率を体感させる」ことを遊びを交えて提示しました。
|
 |

|
 |
移動空間型ARシステム
君塚 史高
情報科学芸術大学院大学 メディア表現研究科 メディア表現専攻
移動空間型ARシステムは電車やバスなどの移動空間内で用いるためのARデバイス、デバイス・コンテンツを配信するためのwebページです。本作品では移動空間に対し普段我々が移動する際に何気なく持ち歩いている携帯電話を利用することによって、移動知覚を強化・拡張するAR体験を提供することを目的としています。
|
 |

|
 |
自閉症って?—我が家のこうちゃん—
阿部 晴果
武蔵野美術大学 造形学部 視覚伝達デザイン学科
自閉症という障害を持ってこの世に生まれてきた私の弟、こうちゃんをめぐる家族のストーリーを主軸に、マンガとテキストで構成して制作した作品です。「自閉症」というものを「1つの個性」として捉えつつ、そんな個性を持った弟から得た私たち家族の経験、彼自身や周囲の人々を通した調査や取材をもとに制作しました。自閉症のことをより多くの人に親しみやすく、身近に感じながら理解を深めてもらえると嬉しいです。
|
 |

|